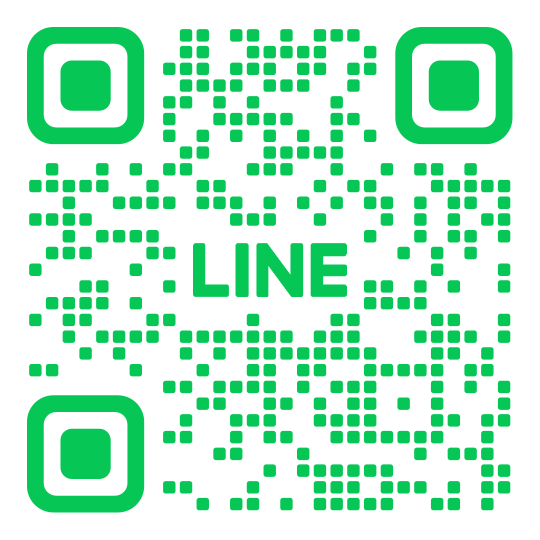本記事の概要
室内空気質の維持は、私たちが健康で快適に生活する上で不可欠です。室内濃度指針値の策定は、2000年代初頭にシックハウス症候群が社会的な課題として認識され始めた時期に行われました。この時期に設定された指針値は、室内空気品質の改善と、当時のシックハウス問題の緩和に大きく貢献しました。
近年では、建材から指針値に含まれる特定の化学物質の使用が減少しており、結果としてこれらの物質が室内で検出されることが少なくなっています。これは、室内濃度指針値が設定された当初の目的が達成されつつあることを示しています。
その一方で、新たに使用され始めた代替物質が室内を汚染しシックハウス症候群が現在でも発生しています。
また室内濃度指針値は長期滞在する室内空間を想定して設定されたものであり、新築の室内空間における化学物質の濃度には直接対応していません。ところがシックハウス症候群の発生のほとんど新築やリフォーム直後に発生しています。
これらの実情を踏まえると、新築時の室内空気質の検査は特に重要であり、指針値に含まれる化学物質だけでなく、新たに使用され始めた代替物質の測定も含めた総合的なアプローチが求められます。
より詳しく知りたい方は以下もご確認ください。
本記事では、室内濃度指針値の設定背景から現在に至るまでの変遷、そしてこれからのあり方について考察します。
この記事では以下の重要なポイントに焦点を当てています。
- 室内濃度指針値の設定背景とその歴史的意義
- 指針値が現代の室内空気質問題に対して果たしている役割の検証
- 室内濃度指針値に対する現代的な課題と疑問の提起
- 指針値の将来性と改善への提案
1. 室内濃度指針値の役割
厚生労働省による室内濃度指針値は、シックハウス問題を含む室内環境における公衆衛生を守るための基準として策定されています。
この指針値は、科学的な知見に基づき、一生涯にわたって特定の濃度の空気を摂取したとしても、健康への有害な影響がないと判断される値を示しています。
ここでの「一生涯」という観点は、長期間の人体への影響を考慮しており、特に敏感な人々の健康を保護するために厳しい基準で設定されています。
空気測定で室内濃度指針値が一時的に超過しても、その状態が持続しない限り、シックハウス症候群が発生するわけではありません。
しかし、室内空気中の微量な物質に過敏に反応する人もいるため、指針値を満たしている場合であっても、すべての個人にとって絶対に安全であるわけではないという点は重要です。
この指針値は、一般国民の健康と安全を守るためのものであり、新しい科学的知見や健康リスクが高い化学物質の情報が得られた場合、室内濃度指針値は適宜見直しや更新が行われ、これにより室内環境の安全性は常に最新の科学的根拠に基づいて保たれます。なお、2024年現在も審議が行われており、継続しています。
こちらの記事も参考に→なぜ室内濃度指針値は追加されなかった?第26回シックハウス問題に関する検討会の概要
2. 室内濃度指針値物質
室内空気中の特定の化学物質に関する人の健康への影響を考慮して、厚生労働省により定められている室内濃度指針値は、揮発性有機化合物(VOC)と半揮発性有機化合物(SVOC)を含みます。これらの化学物質は、人の健康にさまざまな影響を与える可能性があります。
以下の表には、室内濃度指針値が定められている13種類の化学物質のリストです。それぞれに対する毒性指標と設定された室内濃度指針値が記載されています。
室内濃度指針値は、13種類の化学物質を対象としており、これにはホルムアルデヒドやトルエンなど、揮発性成分に分類される化学物質(No.1〜7)が含まれます。これらは気体として存在し、室内空気中で比較的簡単に検出できるため、一般的にシックハウス検査や空気の調査で測定対象となります。
一方、テトラデカンやフェノブカルブといった半揮発性有機化合物(No.8〜13)は、その性質から空気よりも埃に沈着しやすいため、室内の空気測定での検出は難しい傾向にあります。これらの物質は農薬や可塑剤として使用されることが多く、埃と共に移動することがあり、その影響は揮発性化学物質とは異なります。
室内濃度指針値物質は、人への影響や動物実験の結果をもとに化学的な根拠に基づいて設定されています。
| 物質 | 毒性指標 | 室内濃度指針値 (μg/m³) |
|
| 1 | ホルムアルデヒド | ヒト吸入曝露における鼻咽頭粘膜への刺激 | 100 |
| 2 | アセトアルデヒド | ラットの経気道曝露における鼻咽頭嗅覚上皮への影響 | 48 |
| 3 | トルエン | ヒト吸入曝露における神経機能及び生殖発生への影響 | 260 |
| 4 | キシレン | ヒトにおける長期間職業曝露による中枢神経系への影響 | 200 |
| 5 | エチルベンゼン | マウス及びラット吸入曝露における肝臓及び腎臓への影響 | 3800 |
| 6 | スチレン | ラット吸入曝露における脳や 肝臓への影響 |
220 |
| 7 | パラジクロロベンゼン | ビーグル犬経口曝露における 肝臓及び腎臓等への影響 | 240 |
| 8 | テトラデカン | C8-C16 混合物のラット経口曝露 における肝臓への影響 |
330 |
| 9 | クロルピリホス | 母ラット経口曝露における新生児の神経発達への影響及び新生児脳への形態学的影響 | 1 但し小児の場合は 0.1 |
| 10 | フェノブカルブ | ラットの経口曝露におけるコ リンエステラーゼ活性などへ の影響 |
33 |
| 11 | ダイアジノン | ラット吸入曝露における血漿 及び赤血球コリンエステラー ゼ活性への影響 |
0.29 |
| 12 | フタル酸ジ-n-ブチル | ラットの生殖・発生毒性についての影響 | 17 |
| 13 | フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | ラットの雄生殖器系への影響 | 100 |
3. 室内濃度指針値の歴史とシックハウス症候群対策の効果
室内濃度指針値の策定は、2000年前後にシックハウス症候群が社会的な課題として認識され始めた時期に行われました。この時期に設定された指針値は、室内空気品質の改善と当時のシックハウス問題の解決に大きく寄与しました。この成果は、現代においても高く評価されています。
近年、建材から指針値に含まれる特定の化学物質の使用が減少し、結果としてこれらの物質が室内で検出されることが少なくなっています。これは、室内濃度指針値が設定された初期の目的が達成されつつあることを示しています。
新築時の室内空気汚染は対象外?
しかし、新たに使用され始めた代替物質による室内の汚染やシックハウス症候群の発生は現在でも問題となっています。室内濃度指針値は、主に長期滞在を想定して設定されており、新築室内の化学物質濃度への対応は十分に検討されていません。特に、新築時に多く見られるシックハウス症候群の発生を考慮すると、新築時の影響を詳細に調査し、より広範囲にわたる化学物質の検査と評価が必要だと考えられます。
4. 新築時の室内空気質検査と総合的なアプローチ
新たな課題への対応として、室内濃度指針値の定期的な見直しは不可欠です。新しい建材から放出される代替物質や化学物質には、特に警戒が必要です。これらは従来の指針値に含まれていないこともあり、新築やリフォーム直後のシックハウス症候群のリスクを高める可能性があります。
室内濃度指針値は長期的な健康影響に基づいており、新築やリフォーム後の即時対策としては限界がある場合もあります。そこで、指針値に記載されている化学物質だけでなく、新しく使用され始めた代替物質を含む総合的な測定が求められます。特に、総揮発性有機化合物(TVOC)の測定は室内空気質を包括的に評価する上で重要です。
5.「エアみる」を使用した最新の空気測定
「エアみる」を使用した最新の空気測定技術により、室内空気中の100種類以上の化学物質を測定することが可能になります。これにより、シックハウス症候群の原因となる物質を事前に特定し、未然に防ぐ対策を講じることができます。
このような客観的な「見える化」は、消費者に対して安全な家づくりを保証し、信頼を提供する事業者への一つの基準となり得ます。
「エアみる」とは→三浦工業(外部サイト)
エアみるを使った空気測定とは→エアみるを使った空気測定(外部サイト)
まとめ
20年以上にわたり室内空気質の改善に寄与してきた室内濃度指針値も、新しい建材の使用や生活スタイルの変化により、新たな課題に直面しています。私たちの健康を守り続けるためには、指針値を定期的に見直し、新しい測定技術にも対応することが必要です。
空気環境改善研究所は、これらの最新の取り組みを推進し、同時に安全な室内環境を提供する事業者の参加を募っています。
LINE公式アカウントの登録をお勧めします。
空気に関する最新情報やお知らせを定期的に受け取りたい方は、ぜひLINE公式アカウントに登録してください。Line公式では空気に関する相談も受け付けております。気軽に登録して、ご利用ください。